排泄ケアは「生きるリズム」と向き合う仕事
「おむつ依存」や「便秘」に悩む利用者さんと接するとき、
私たちはつい「身体的ケア」だけに目が向きがちです。
でも、排泄トラブルの背景には
- プライドを傷つけたくないという 心の壁
- 生活リズムの乱れから生まれる 孤独感
- 自分の体の変化への 戸惑い
――こうした「声にならない声」が潜んでいること、気付けているでしょうか?
厚生労働省の調査では、
介護職員の約67%が「排泄ケアのストレス」を離職理由の一つに挙げています。
数字の裏側にあるのは、
「どうケアすればいいかわからない」という無力感。
「時間がないから」とおむつに頼り切る罪悪感。
――現場のジレンマが、人材流失に直結しているのではないかと、
排泄ケアの視点から見えてくるものがあります。
「ケアは心の声を聴く作業」
介護の現場から私が学んだのは
「便の回数より、排泄時の表情が全てを物語る」ということ。
ある認知症の女性は、下痢が続くたびに子どもの頃の厳しいしつけを思い出しているようでした。
別の男性は「夜間のおむつ交換だけが、職員と会話できる時間」と密かに心待ちにしていました。
あなたの施設では、こんな「声」を拾えていますか?
・トイレの失敗を怒られた子ども時代のトラウマ
・排泄介助時の「手の温もり」に感じる安堵
・オムツのフィット感から生まれる自己肯定感
大切な人にさえ見せるのは恥ずかしい部分。
そのケアについては、私もまだまだ人間力が追いつきませんが
それでも、今からでもできることが排泄ケアに関わる介護職にはあると思っています。
まずは「排泄したものを5秒観察すること」から始めてみましょう。
出たか出ないか、ではなく色や形、
そばにいる介護職だからこそ読み解ける、大切なその人からのお便りです。
次の投稿では、
「観察→対話→環境改善」の3ステップで
「排泄のリズム」を取り戻す具体的な手法 をご紹介してみたいと思います。
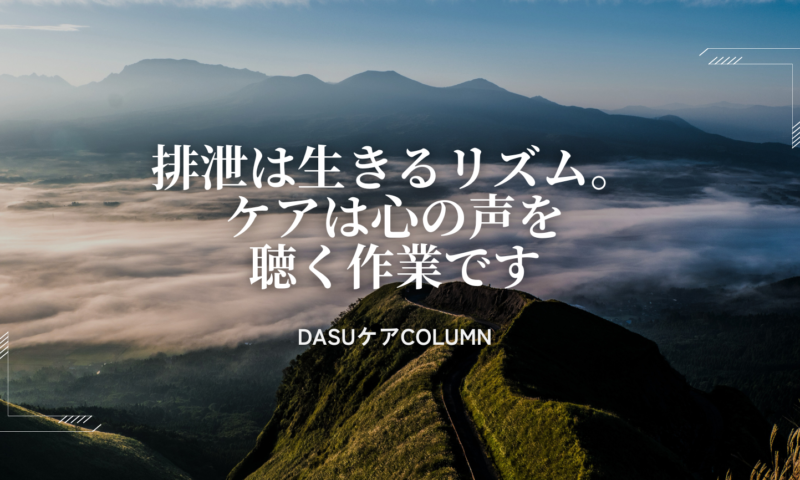


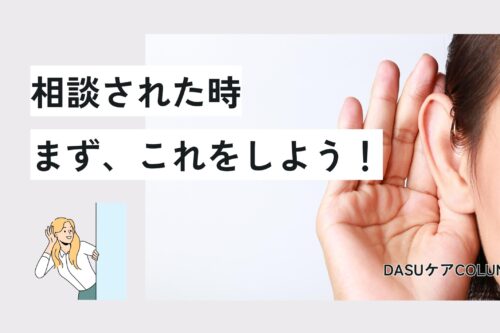


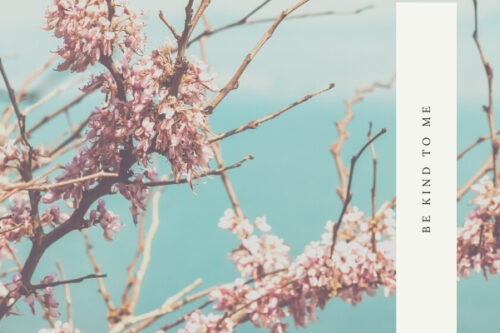

この記事へのコメントはありません。